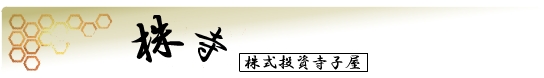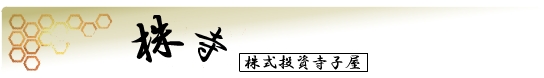PERって・・・
世間に出回っている株式投資の本には必ずといっていいほど、"PER"という指標が出てきます。
ここで、PERに関する私個人の解釈を説明します。
PERとは、現在の株価が1株当りの利益に対して何倍の値段で売買されているかを示す指標です。
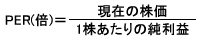
この値が大きければ大きいほど現在の株価が割高になっている。反対に少なければ少ないほど
現在の株価は割安になっていると判断します。株式投資は安いときに買って、高いときに売るというのが
基本動作なので、この指標を頼りに売買する人が多いようです。
しかし、ここで問題があります。PERの式の構造を見ると、分母は1株当りの利益となっています。
これは当期純利益から株数を割ったものです。株式を追加発行したり、株式を分割した場合は、発行株式数の変動に伴い、
この値は減少します。ただし、分割などは株価もそれに伴って機械的に減少しますが、分割を材料に株が売られたり、
買われたりすることもあります。
要するに、株式が増えるとPERは業績や、市場の状態などとは関係なく変動しますし、
それにつられて発生する投資家の売買が原因で変動します。
また、株価を1株当りの利益で割ると実際の企業の成長性に対して割高とか、割安だとかが本当に判断できる
ものなのでしょうか? 1株当たりの利益が完全に自分に返ってきたと仮定すれば、その1株を買える株価が高い、安いと判断できます。
しかし、人は将来成長する可能性のある企業に投資します。そのため、現時点でのPERがある程度高くても成長性のある企業には
投資してよいと考えるはずです。
実際、PERを説明している本では成長している優良株については、PERは高くなると書かれています。
また、そういう株はPERが高くても株価は上昇します。
一方、数多くの投資本に見られるように、このPERを使って
売買している人がいるのは事実です。この数値は株価が割安・割高だという指標というより、
人気指標と考えるべきではないでしょうか。ということは、この指標は別の意味で利用価値があるといえます。
PERが高ければ割高と判断して売却する人が多くなる、PERが低ければ買いに入る人が多くなるといった具合に、そういう人たちの
売買のタイミングをある程度把握することができます。これにより、どの辺りの株価が天井となり得るか予想する
ことができます。それが予測できれば、例えば株価が天井をつける前に売却し、利益を確保することができます。
もちろん、PERによる推測だけでは外れることが多いかと思いますが、一つの参考指標としては機能すると思います。
前へ | 次へ